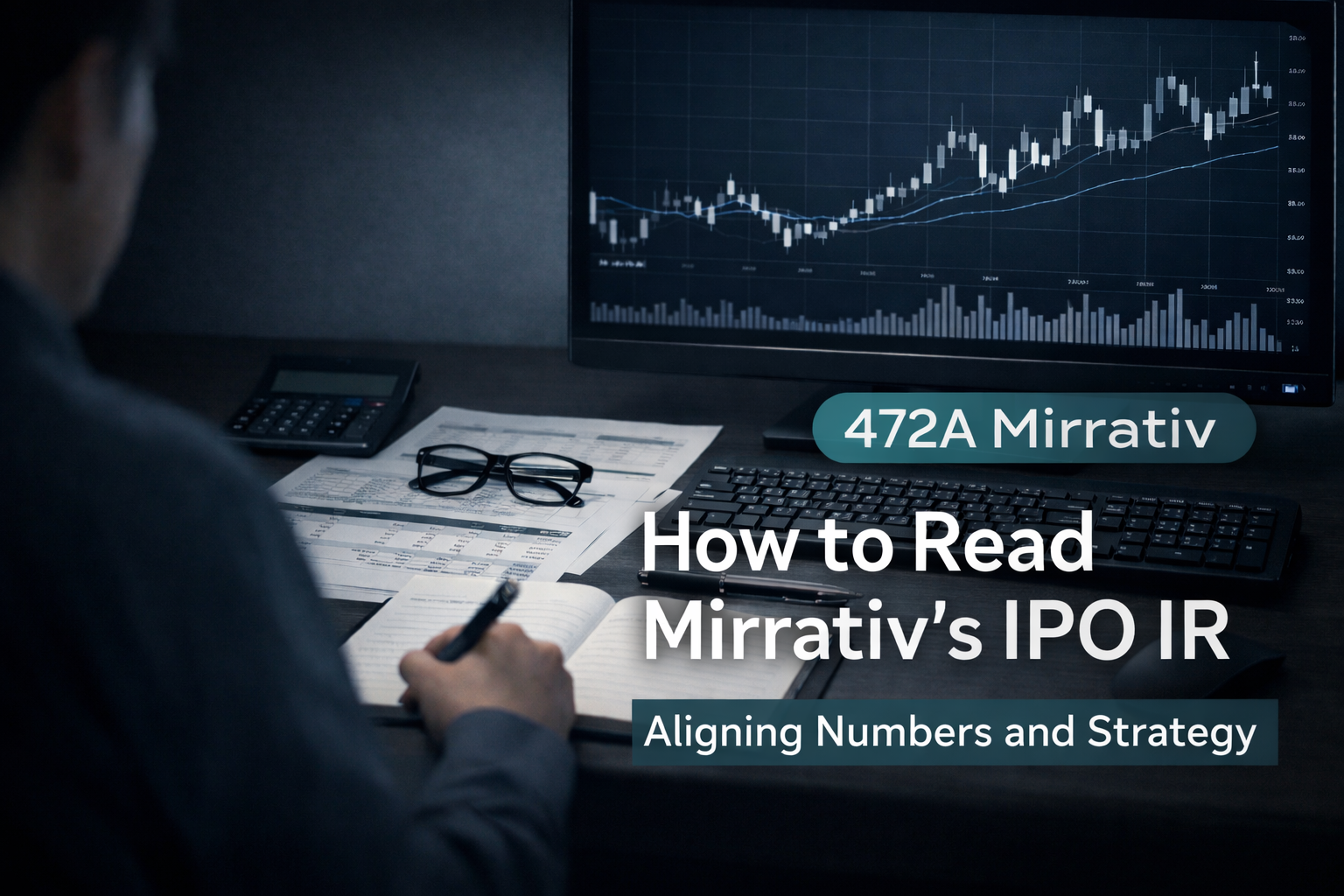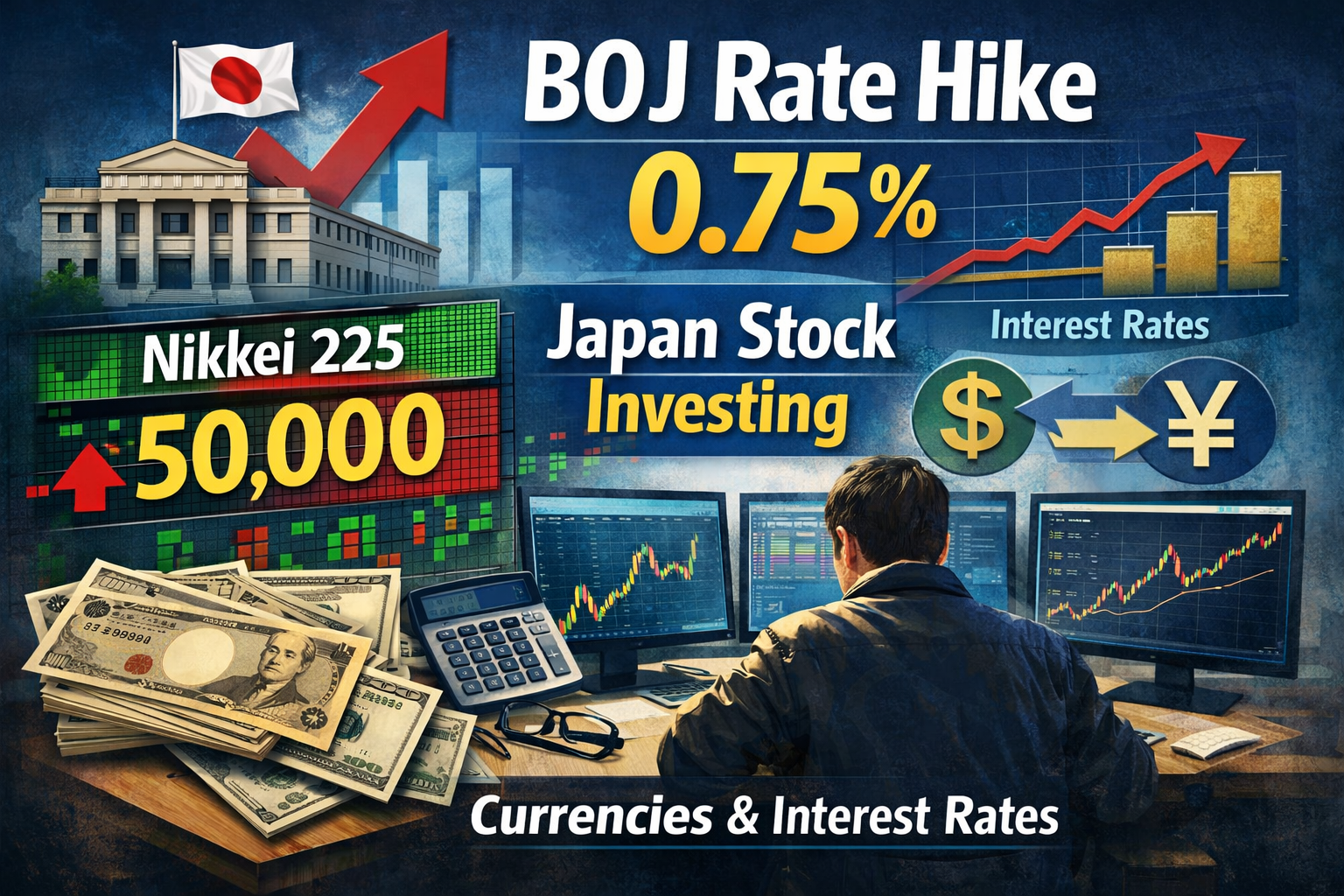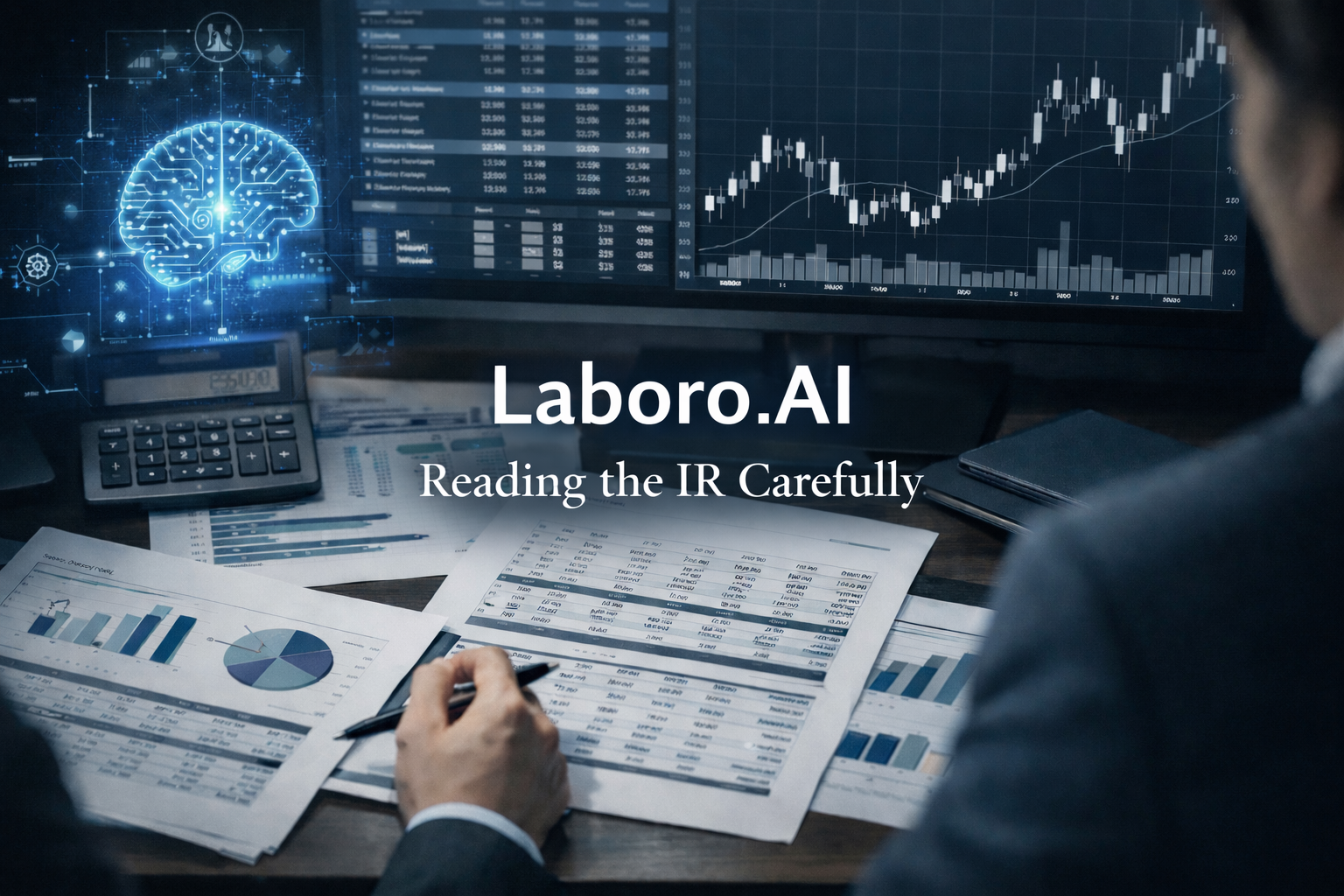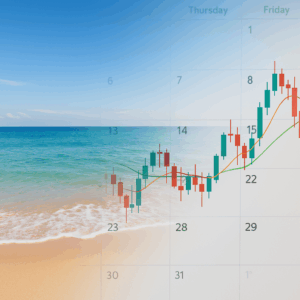相場が動く直前には、必ず何かが起きている。
多くのトレーダーはその「動いたあと」に騒ぎ出すが、本当に結果を出す者は「動く前」に静かに仕込みを終えている。豪ドル円。2025年7月。今、この通貨が持つ「緊張感」に、あなただけは気づけているだろうか。
金利は据え置かれた。
雇用は堅調を維持したように見える。
チャートは96円台を回復し、市場は一見落ち着いている。
だが、その静けさの裏に、市場は確かに揺れている。
トランプ再登場をにらんだ米金利観測、中国経済指標と資源価格の微妙な変調、そして今月17日に控える豪6月雇用統計。
この記事では、ファンダメンタルズ分析を用いて、こうした材料をすべて整理。
専業トレーダーとしての経験に基づいて、中級トレーダーに向けて「2025年7月以降、豪ドル(AUDJPY)はどこへ向かうのか」を考える。「自分の分析に自信が持てない」「予想の組み立て方を知りたい」という初級者にとっても、きっと役立つ視点を提供できるはずだ。
単なる予想ではない。
相場の呼吸を読み、勝ち筋だけを抜き取る。
そのヒントをすべて、この1本に詰め込んだ。
豪ドルの基礎地合い|「高金利通貨」の正体を再確認
豪ドル円(AUDJPY)は、よく「高金利通貨」と呼ばれる。
それは表面的な事実に過ぎない。
重要なのは、その金利がどんな経済環境の中で維持されているのか。
そして、今後どう変化するか。その本質を見抜くことだ。
豪州経済の現在地|インフレと雇用の二律背反
2025年7月現在、オーストラリア準備銀行(RBA)の政策金利は3.85%で据え置きとなっている。市場では0.25%の利下げが予想されていたが、RBAはそれを退けた。この決定の背景には、「インフレリスクがよりバランスの取れた状態にある」「雇用市場は依然として堅調」という認識がある。
実際、豪州の雇用市場は表面的には安定している。失業率は、6か月連続で4.1%という低水準を維持。新規雇用者数のブレはあるものの、全体としては大崩れしていない。ただし、これは「今のところ」の話だ。
なぜ「高金利」が維持されてきたのか
もともと、豪ドルは資源国通貨としての特性を持ち、金利が高めに設定されやすい。特に、インフレに敏感な政策スタンスが長らく続いてきた。さらに中国への輸出依存が強く、中国経済の回復と資源需要の増加が支えとなってきた側面もある。
だが、ここにきてその構造が揺らいでいる。中国経済の回復は鈍化し、鉄鉱石や石炭といった主力輸出品の価格も不安定だ。にもかかわらず、RBAは「まだ利下げしない」と判断した。この判断の根拠が、今月17日発表の6月雇用統計で裏付けられるかどうか。これが次の山場になる。
豪ドルにとっての「金利」はどこまで武器になるのか
トレーダーの視点から見ておくべきなのは、3.85%という金利水準が市場にとって「十分な保有動機」になっているかどうかという点だ。円やユーロといった低金利通貨に対しては、まだスワップ狙いの買いが入る余地がある。
だが、最近の傾向としては「金利が高いだけでは資金が集まらない」構造に変わりつつある。市場は金利だけでなく、次の一手(利上げか利下げか)を読み、先回りして動く。
つまり、「高金利通貨」としての豪ドルの優位性は、もはや金利の絶対値ではなく、金融政策の方向性にかかっている。ここを見誤ると、相場は逆に走る。
金利据え置きの裏側に潜むリスク
表面上はポジティブ。だが、内実はそうでもない。
それが、7月8日の豪準備銀行(RBA)による政策金利「据え置き」判断の正体だ。
マーケットが見落とした「据え置きの理由」
今回の据え置きには、決して強気の姿勢は含まれていない。RBA自身がこう述べている。
「インフレ率が持続的に2.5%に到達することを確認するため、もう少し情報を待つことができると判断した」
これはつまり、「利下げしたいが、その根拠がまだ弱い。雇用が崩れれば迷わず下げる」という本音の表れだ。市場はこの発言を「まだ様子見」と好意的に受け取ったが、専業トレーダーからすれば、これは下げる準備に入ったというシグナルにしか見えない。
重要なのは、「インフレ率が低下傾向にある」という事実に加え、今後の雇用統計が利下げの口実になるかどうかが、焦点になっているという点だ。
雇用統計が崩れれば、一気に利下げに傾く構造
7月17日に発表される豪6月雇用統計。予想は以下のとおりだ。
- 新規雇用者数:2.00万人増(前回:-0.25万人)
- 失業率:4.1%(前回と同じ)
ここで大事なのは、新規雇用者数が回復するかどうかではない。予想が外れたときにマーケットがどう反応するかを読むことだ。
たとえば、前回5月は市場予想がプラスだったにもかかわらず、結果はマイナス。そしてそのとき豪ドルは急落した。今回も、もし2万人という予想が外れ、再びマイナスになるようなら、マーケットの判断は早い。
RBAはもう利下げを視野に入れており、雇用統計がそれを後押しすれば、8月の会合で利下げが現実化する。すでに、政策金利3.60%への利下げは、一部マーケットで40%近く織り込まれつつある。
つまり、現在の「豪ドル高」は、きわめて不安定な仮定の上に成り立っている。
「据え置き=強い」とは限らない
トレーダーとして特に注意しているのは、市場が好感しすぎるときほど、崩れやすいという点だ。今回の据え置きに対し、多くのレポートやメディアは「豪ドル買い継続」と結論づけている。
だが、それは極めて短期的な反応でしかない。RBAの本音は「利下げタイミングを測っている」であり、データ次第ではそのスイッチがいつでも入る。
市場は、利下げを始めた中央銀行の通貨を長期的に買い続けることはない。したがって、豪ドル(AUDJPY)が本当に上昇を続けるなら、それは雇用統計が強く出た場合に限られる。それ以外では、反落のリスクが極めて高い。
豪雇用統計の読み方|予想と結果、どちらに張るべきか
相場で勝つには、「数字そのもの」よりも、「その数字が市場にどう受け取られるか」を読む必要がある。特に、7月17日(水)10:30発表予定の豪6月雇用統計は、単なる経済データではない。豪ドル円(AUDJPY)の進路を決めるトリガーだ。
今回の雇用統計に対する市場の「前提」
市場はすでにある種の期待で動いている。つまり、「前回(5月)が弱かった反動で、今回は持ち直すだろう」というストーリーが織り込まれている。
- 前回:新規雇用者数 -0.25万人(予想は+1.5万人)
- 今回の予想:+2.00万人
予想そのものは控えめな数字に見えるが、問題は「前回悪かったから今回は良くなるはず」という心理が市場全体に広がっていることだ。
この心理が作り出すのは、強めの数字が出ても大きな反応が起きにくい一方で、ネガティブサプライズが出たときの反応が極端になりやすい地合いだということ。
つまり今回、仮に2万人の雇用増が実現しても、「ああ、予想通りだな」で終わる可能性が高い。だが、もし1万人未満、あるいは再びマイナスとなった場合、RBAの利下げ観測が一気に現実味を帯びてくる。
数字以上に大事な「失業率の形」
失業率の予想は4.1%と、前回と同じだ。しかし、ここにも落とし穴がある。失業率は、新規雇用者数がプラスであっても、労働参加率が上がれば逆に上昇することがある。
市場がこれをどう解釈するかによって、相場は逆に動くことがある。
- 新規雇用者数が予想を超えた → AUDJPY上昇
- しかし、失業率が上昇 → 利下げ観測が残る → AUDJPY反落
このように、「雇用者数」と「失業率」は単体では意味を持たず、セットで読み解く必要がある。
予想に張るな、ズレに張れ
ここで僕が注目するのは、予想に合致した時ではなく、予想とズレた時の反応だ。
- 市場が「強い数字」を前提に動いているときは、それが裏切られた瞬間に大きな振れが起きる。
- 逆に、予想通りだった場合は、ポジションの巻き戻しが起きやすく、すでにロングに偏っていた市場は一時的に利確に傾く。
だから僕は、「数字がどうなるか」ではなく、「ズレた時に誰がどう動くか」に張る。
そして今、相場はロングに偏っている。つまり、わずかな悪材料であっても、下方向に揺れやすい。
米国要因の影響力とリスク資産としての豪ドル
豪ドル(AUDJPY)は、オーストラリアの事情だけで動く通貨ではない。実際には、米国の金利政策、株式市場、さらにはトランプ再選のシナリオまで、外部要因によって揺さぶられる構造にある。
米国金利と豪ドルの微妙な関係
2025年7月、米国の金融政策は方向感を失っている。FRBは利下げに向かう兆しを見せながらも、経済指標によって毎週のように姿勢が変わる。とくに、7月15日に発表される6月のCPIが大きな注目を集めている。
米CPIが予想を上回れば、FRBの利下げ観測が遠のき、米ドル高が進みやすくなる。そうなると、豪ドルは相対的に売られやすくなる。一方で、CPIが弱ければリスク選好が戻り、資源通貨の豪ドルは買われる可能性がある。
だが重要なのは、豪ドルが安全資産ではなく、いわば世界経済の体温計のような性質を持っているという点だ。景気が良いときにはリスク選好で買われやすい。だが、不透明感が漂うと、真っ先に投げられるのもこの通貨だ。
いまの米国は、利下げを望む政治的圧力と、それに抗おうとするFRBの間で揺れている。加えて、11月の大統領選を前に、トランプ再登場のリスクもマーケットに織り込まれ始めている。これらが複雑に絡み合う中で、豪ドルは外的要因に振り回される展開が続く。
株式市場と豪ドルのシンクロ
7月上旬、米S&P500は過去最高値を更新した。これを背景に、豪ドルは96円台を回復した。株高=リスクオン=豪ドル買い。この流れはセオリー通りに見える。
だが、相場がセオリーに忠実すぎるときほど、反転は突然やってくる。米株高に対する期待感が剥がれた瞬間、豪ドルは一転して調整局面に入るリスクがある。特に、米金利が不安定な中での株高は、いわば足場の不安定な高所作業のようなもの。ひとたび崩れ始めれば、その影響は資源通貨に直撃する。
豪ドルは、自国の経済データだけでなく、こうした米国要因の空気感にも敏感に反応する。これはトレーダーとして見逃してはならない事実だ。
チャートの地図|豪ドル 96円台の意味
豪ドル円(AUDJPY)は、2025年7月上旬にかけて5カ月ぶりの高値圏に達した。96円台後半。この水準は、単なる数字ではない。過去に幾度も反発や反落を繰り返した、相場に刻まれた記憶が集中する価格帯だ。
96円台は通過点か、壁か
チャートを見ると、96.80円付近は2024年12月以来のレジスタンスだった。2025年2月にもこの水準で上値を止められている。その後は長いあいだ94円台での横ばいが続き、7月に入ってようやく再びこの水準に接近してきた。
この上昇には、米株高や金利据え置きのサプライズなど、いくつかの後押しがあった。だが、それらの多くは短期的な材料に過ぎない。
つまり、今の96円台は、強いファンダメンタルズによって支えられた堅固な上昇というよりも、ポジティブ材料が一時的に重なった偶発的な高値に近い構造をしている。
このため、豪雇用統計や米CPIの結果次第では、一気に95円台前半、さらには94円台後半までの調整も想定しておく必要がある。
上値のターゲットと反落のシナリオ
仮に市場が雇用統計やCPIを好感し、リスク選好の流れが続いた場合、次の上値ターゲットは明確だ。97.20円付近、そして98円台前半。このあたりは、2023年後半にも到達していた高値圏であり、オプションのストライクも集中している。
だが、ここからの上昇は一段と重たくなる。というのも、年初から中長期の売りポジションを抱えていた機関投資家が、ちょうどこのあたりで利確や建玉調整を入れてくる可能性が高い。実際、2024年末もこの水準で頭打ちになった。
つまり、97円台は「抜ければ一気」と言われがちだが、実態としては分厚い売りが蓄積された圧力のゾーンでもある。
一方、下値については、95.20円付近に直近の押し目支持がある。ここを割り込むようだと、雇用統計への失望や米経済への不安が急速に台頭し、94円後半までの反落が視野に入ってくる。
短期的なレンジとしては、
- 上限:97.20円〜98.00円
- 下限:94.50円〜95.00円
このゾーン内での上下動をイメージしておくのが現実的だ。
短期的な攻防ポイントと勝ち筋の作り方
豪ドル(AUDJPY)が96円台に乗せている今、相場にいる多くのトレーダーは、上か下かのどちらかにポジションを傾け始めている。だが、この局面では、単純な順張りや逆張りでは勝ちづらい。重要なのは、「相場がどこで迷い、どこで動くのか」を見極めることだ。
攻防ライン1:95.70円台の押し目
まず注目すべきは、95.70円付近。この水準は、今月に入ってから何度もサポートとして意識されてきた。96円台で利確売りが出たとしても、ここでいったん下げ止まる可能性がある。
短期で買いを狙うなら、このラインでのプライスアクションに注目したい。具体的には、長い下ヒゲを伴う陽線や、1時間足レベルでのダブルボトム形成が確認できれば、ストップを浅めに置いた買いが機能しやすい。
ただし、この水準を明確に割り込んできた場合は、逆に流れが加速することがある。その際は、下の支持帯である95.20円台を目指す展開に切り替わる。
攻防ライン2:96.80円台の上値抵抗
一方、上昇のターゲットとなるのが96.80円台。この水準は、7月10日に一時的にタッチしたが、終値では維持できなかった。ここを再びトライし、上抜けに失敗した場合は、ショートの好機となる。
とくに、東京時間でジリ高が続いたあと、欧州入りで失速するような展開は要注意。短期筋の利確と逆張りの売りが重なるポイントでもあり、瞬間的に1円以上の値幅が出ることもある。
96.80円を超えてきた場合でも、オーバーシュートに注意したい。97円台はオプション絡みの売りが控えており、抜けても連続性が続くかどうかは不透明だ。
利用すべきテクニカル
- 4時間足の200EMA
- ボリンジャーバンド(±2σ)
- 1時間足の転換線・基準線(雲の上下)
これらをベースに、ブレイク狙いではなく「反転ポイント」での仕掛けが今月は有効だ。特に、豪ドル(AUDJPY)は一方向に長く伸びるより、何度も折り返す習性がある。天底を取ろうとするのではなく、相場の迷いを味方につけることが重要だ。
8月RBA会合に向けて、どう構えるべきか
7月の相場は、8月に控える豪準備銀行(RBA)の政策会合に向けた地ならしの時期でもある。市場はすでに、その先の利下げをどこかで織り込もうとしている。そして、今の据え置きという判断も、単なる現状維持ではない。むしろ、「利下げへの布石」と捉えたほうが、トレーダーとしては正確だ。
7月雇用統計の結果次第で、8月は動く
繰り返しになるが、7月17日に発表される雇用統計の結果が、RBAのスタンスに大きな影響を与える。もし新規雇用者数が伸び悩み、失業率が微増するようなら、8月会合での利下げ議論は一気に現実味を帯びる。
実際、据え置き後の声明でも「インフレリスクはよりバランスの取れたものになっている」と明記されており、インフレ抑制が目的だった高金利政策の転換が視野に入っている。
これは、長期で豪ドルを買い支えてきた投資家にとっては、ロジックが崩れるポイントでもある。利回り狙いの買いは剥落し、実需や投機のフローも逆回転を始める。
つまり、8月のRBA会合は、相場の「上げ止まり」を確認する場になる可能性がある。
利下げが決まったとき、豪ドルはどう動くか
過去の経験上、利下げ自体はある程度織り込まれていれば暴落の引き金にはならない。だが、問題はその後のガイダンスだ。
- さらに追加の利下げ余地を示唆するか
- 景気減速を理由に慎重姿勢を強めるか
- インフレ鈍化が長期化するシナリオを提示するか
これらのメッセージが市場の失望を誘えば、豪ドルは下方向に加速する。逆に、利下げをしても「単発で終わる」と明言すれば、むしろ反発する可能性もある。
ここで重要なのは、トレーダーがどこで情報に先回りし、どこで反応に乗るかを決めておくことだ。8月会合を受けて動き出すのを待つのではなく、7月中に構築された地合いのなかに、「動く前兆」が必ずある。
戦略的ポジション構築|トレードプランの実例
相場を読み解くだけでは、まだ半分。重要なのは、そこからどう張るか。ここでは、実際に僕が構築しているトレード戦略の一部を紹介する。短期と中期、それぞれの立場から、豪ドル円(AUDJPY)のエントリーポイントとリスク管理を明確にしていく。
短期トレード:逆張りと押し目買いの切り替え戦略
現時点でのレンジは、94.50円〜98.00円と広めに見ているが、実際のエントリーはもっと絞り込む必要がある。
たとえば、96.80円台に到達した直後の値動き。ここで勢いが鈍れば、上昇のモメンタムが息切れした合図になる。欧州時間の入り口で下げ始めたら、97円手前で売りを構える。
- 売りエントリー:96.90円前後
- 損切りライン:97.30円超え(オーバーシュート警戒)
- 利確ターゲット:95.70円〜95.50円付近
逆に、95.20円を割らずに反発した場合は、押し目買いへ戦略を転換。
- 買いエントリー:95.30〜95.40円
- 損切りライン:94.80円割れ
- 利確ターゲット:96.30円〜96.50円
豪ドル円(AUDJPY)は、指標直後の一方通行よりも、だましと巻き戻しを伴うパターンが多い。だからこそ、「初動に逆らうエントリー」は避け、あくまで動きの確認後に仕掛ける。
中期トレード:雇用統計とRBA会合をまたぐ構え
中期では、雇用統計の結果を受けての変化が大きな材料になる。想定されるシナリオは三つある。
- 雇用統計が強い → AUDJPY上昇継続 → 97.50円超えも視野
- 雇用統計が中立 → 上昇失速 → 95円台への戻り
- 雇用統計が弱い → 利下げ観測急拡大 → 94円台前半へ急落
このなかで、最も取りやすいのは、雇用統計でポジティブに反応した後にRBAで失望するパターン。相場は先に買われ、あとで売られる。この流れを見越して、上昇の終盤に売りを構築する。
- 売り構築:雇用統計後に96.80円を超えたら、段階的に分割エントリー
- 分割3回:96.90円、97.10円、97.30円
- 損切り:97.60円台に明確な定着
- 利確:95.00円〜94.50円ゾーンで部分利確
このポジションは、8月のRBA会合をまたぐ。利下げの有無に関係なく、「不透明感を嫌う売り」が発生しやすいタイミングでの構築を狙う。
リスク管理とマインドセット|豪ドル円を扱う者が陥る「負け方」
豪ドル円(UADJPY)は、ドル円やユーロ円と違って、「気配が変わった瞬間に逆に走る」性質を持つ。だから、トレードにおけるリスク管理とマインドセットは、他通貨以上にシビアでなければならない。
豪ドル特有の「逆流」で負ける
まず知っておくべきは、豪ドル円(AUDJPY)はポジションが傾きやすい通貨ペアだという点だ。特に今のように金利が高止まりし、市場が据え置きに安心した直後は、買いが一気に入りやすい。その一方で、ちょっとしたマイナス材料でいきなり利確売りとショートが重なり、1円以上逆に走る場面がある。
ここで負けるのは、決まって「遅れて乗って、すぐに振り落とされた」タイプのトレードだ。
たとえば、雇用統計の直後に豪ドル円が跳ね上がったとして、その場で飛び乗ってしまうと、10分後には逆流が始まり、元の水準に戻っていることもある。豪ドル円はこのパターンが非常に多い。
だから僕は、豪ドル円においては「動いたあとに乗る」ことを極力避けている。動く前、あるいは反転が明確に見えた後にだけ張るようにしている。
なぜ豪ドル円は想定外に走るのか
それは、材料の性質にある。豪ドルはオーストラリアの要因だけでなく、中国の指標、米国の金利、S&P500の動き、さらには資源価格やトランプの発言まで、極端に広い影響を受ける。これは「ファンダメンタルズの交差点」とでも呼ぶべき通貨だ。
だから、値動きが急変するときは、テクニカルでは読み切れない理由で裏切られることが多い。
こうした豪ドルの特性を知っているトレーダーは、必ず逃げ場を前提にポジションを持つ。たとえば、エントリー時点で損切りまで10pips以内に設定できないなら、最初から入らない。逆に、入った後に逃げ場がなくなったと判断したら、プラスでも即刻利確する。
ここで利を伸ばそうとして戻されるのが、豪ドルトレードで最も多い「利益の帳消し」だ。
マインドではなく、通貨に合わせる
つまり、必要なのは精神論ではない。通貨の性格に合わせた管理の仕方だ。
豪ドル円に対して僕が常に意識しているのは、「読みが当たっても、途中で振り落とされる可能性がある」という前提。そのうえで、どこで入るか、どこで逃げるか、どこまで許容するかをあらかじめ書き出してから入る。
感情を抑えるのではなく、仕組みでミスを減らす。それが豪ドル円という通貨を扱う者の最低限のマナーだと思っている。
結局、7月後半の豪ドルはどうなる
7月後半、豪ドル円は上値が重くなっていく可能性が高いと、僕は見ている。
ただし、「下落トレンド入り」と言い切るにはまだ早い。
正確には、天井をつけにいく途中段階にあるというのが、僕の現時点での見立てだ。
その理由は、大きく3つある。
金利据え置きの「出尽くし感」
RBAが7月に金利を据え置いたことに対して、市場は一時的に好感した。確かに、据え置き自体は豪ドル買いの材料となった。ただ、これはあくまで「予想に反した」というだけの短期的インパクトに過ぎない。
市場が本当に織り込みたいのは、「次の方向性」だ。8月の利下げ可能性が依然として消えていない以上、今回の据え置きに過剰に反応した買いは、すでにピークを迎えていると見ている。
7月中旬以降、出尽くし感がじわじわと売り圧力に転化していく可能性がある。
豪6月雇用統計の内容次第で市場が傾く
次に注目すべきは、7月17日に発表される豪6月雇用統計だ。
前月(5月)の雇用統計では予想を下回る結果が出ており、マーケットは次の数字に極めて敏感になっている。もし今回も期待に届かない内容であれば、市場は一気に「8月利下げ」へ傾き、豪ドルは売られやすくなる。
特に豪ドル円においては、日銀が動かない以上、豪ドル単体の材料が値動きの全てになる。この「豪単独材料相場」では、一度のデータで流れがひっくり返るのが常だ。
7月後半の最大の分水嶺は、この指標になる。
株高の終焉が為替に波及する可能性
もう一つ、忘れてはならないのが米国株の状況だ。
7月上旬にS&P500が過去最高値を更新したが、その背景にはAI関連銘柄に偏った買いがあった。もしこのテーマが一巡し、利益確定の流れが広がれば、リスクオンムード全体が冷え込む。
豪ドルは典型的な「リスク選好通貨」だ。株安が始まれば、真っ先に売られる対象になる。
さらに言えば、米国では7月30日〜31日のFOMCに向けて、利下げを巡る期待と警戒が交錯しはじめている。このタイミングで株価が調整すれば、豪ドルもその余波を受ける可能性がある。
7月後半、豪ドル円は「天井形成期」に突入
すべてを総合すると、今の豪ドル円は「勢いのある上昇トレンド」ではなく、「上昇の最終段階にある」と考えるのが自然だ。
僕自身は、96.50〜97.00円台のレンジで戻り売りのチャンスを狙う構えでいる。指標で突発的に98円を試す場面があっても、そこから先はロングを維持するリスクが高すぎる。
短期的に買いを狙うなら、「指標の直後、反応を見てから」。中期的に構えるなら、「次の下落への第一歩を捉える」姿勢のほうが、豪ドルという通貨の性格に合っている。
投資家として重要なのは、「いまのトレンドに乗ること」ではない。「そのトレンドがいつ終わるかを読むこと」だ。
7月後半の豪ドル円。これは、まさに終わりが始まるタイミングだ。
STEPで学ぶ 豪ドル円戦略をさらに深く理解する
7月の豪ドル円(AUDJPY)を狙うなら、単体の通貨分析では不十分だ。
今の市場は、ドル円やユーロドルを含めた通貨間の力関係のなかで動いている。
ここでは、2025年7月時点のファンダメンタルズを土台に、豪ドル円を中心としつつ、主要通貨の動向も踏まえた戦略の構築を3段階で整理した。トレード判断の再現性を高めたい中上級者に向けて、具体的な視点を深掘りしていく。
「なぜ通貨に強弱があるのか」「どこに注目すべきか」
トレードで勝てるようになる第一歩は、通貨の本質的な強さを見抜く力を養うことだ。
豪ドルの動向は、対ドル・対ユーロの相関でも大きく左右される。
クロス円だけを見ていては相場の全体像は掴めない。
豪ドル円を動かしている大本の資金フローは、結局のところドル円が握っている。
だからこそ、円の変動要因・方向性を読むことは、豪ドル円戦略においても最重要だ。
2025年7月、豪ドル円の勝負どころはここだ
今月の豪ドル円は、静かにうねりながら、じわじわと均衡を崩しつつある。
上昇を支えてきたのは、RBAの金利据え置きという予想外の判断と、それに反応した短期筋の買いだった。だが、そこに「継続性」はまだ見えていない。
7月17日発表の雇用統計。ここが、ひとつの分岐点だ。
この数値次第で、8月利下げ観測の強さが大きく変わる。失業率が上振れすれば、RBAは早期に利下げへ舵を切るだろう。逆に労働市場の底堅さが示されれば、据え置きの正当性が増し、豪ドルの買い戻し圧力が強まる。
つまり、今月は「政策期待の調整相場」だ。
豪州だけではない。米CPIや中国指標の影響も加わり、値動きは細かく分岐していく。
その中で、僕が注目しているのは次の2点。
- 95円台半ば〜96円後半のレンジ上抜けに失敗したときの売り圧力
- 雇用統計直後の1時間足の出来高と勢いの偏り
これらは、短期・中期どちらにも活かせる視点だ。今月の相場は、長期トレンドではなくタイミングを狙うトレードが向いている。
予想レンジは、94.30〜98.10円。
ただし、これは参考値にすぎない。肝心なのは「どの場面で、どう張るか」だ。
7月の豪ドル円は、焦点を絞って戦えば、十分に勝機がある。
だが、流れに乗り遅れると、判断を誤らせるノイズも多い。
動くべきタイミングを見誤らないこと。
これが、7月の豪ドル相場を攻略するための、最も重要なポイントだ。