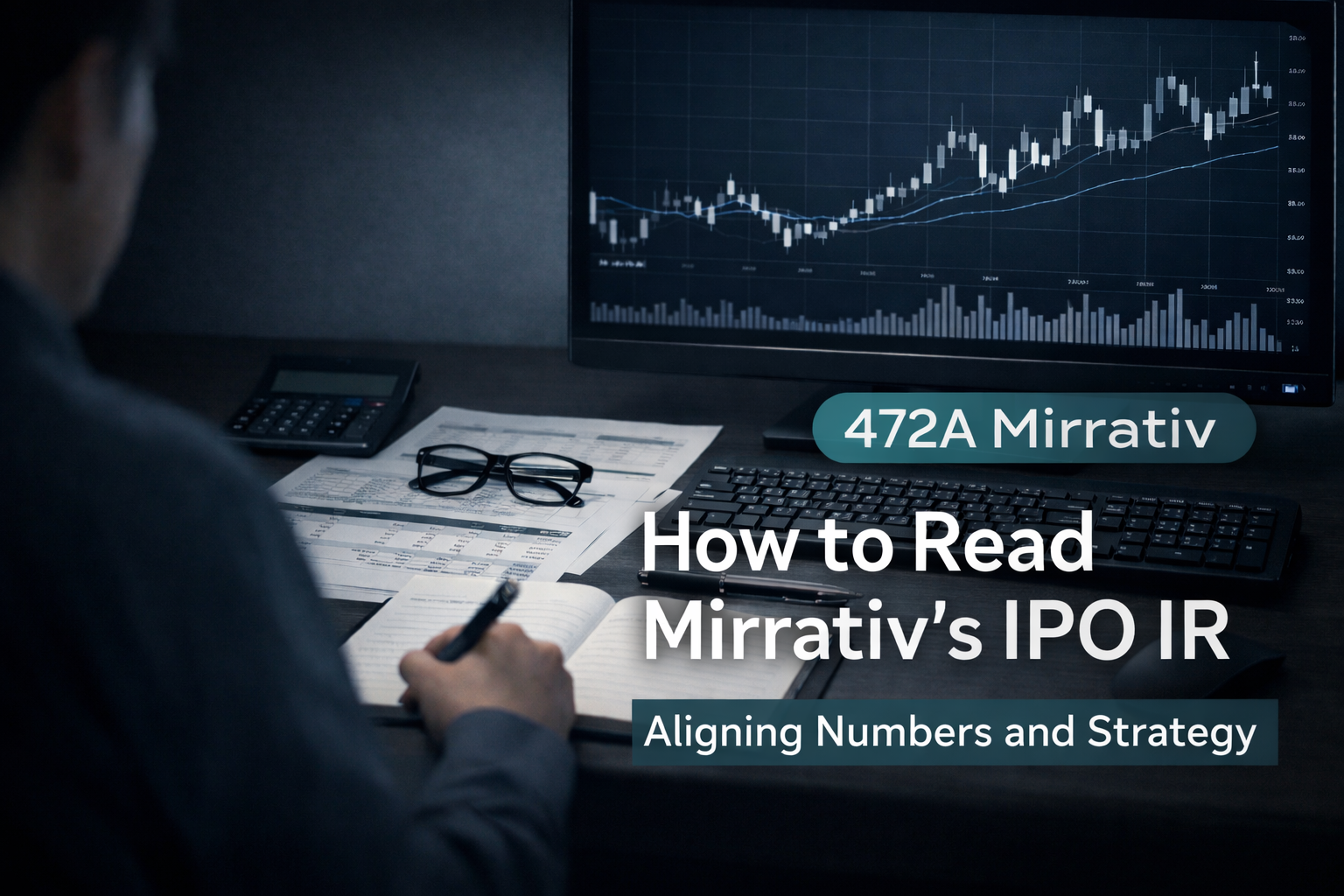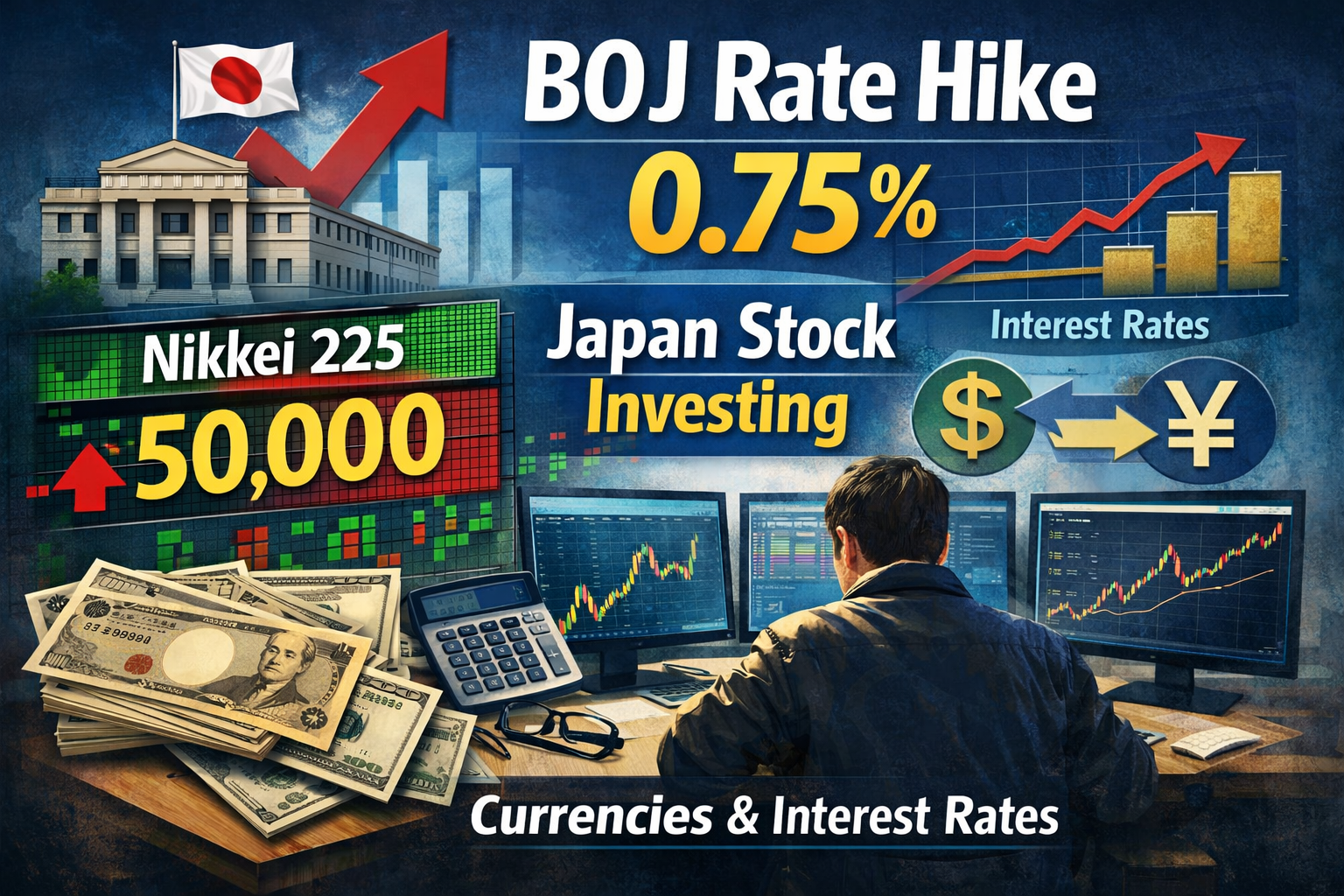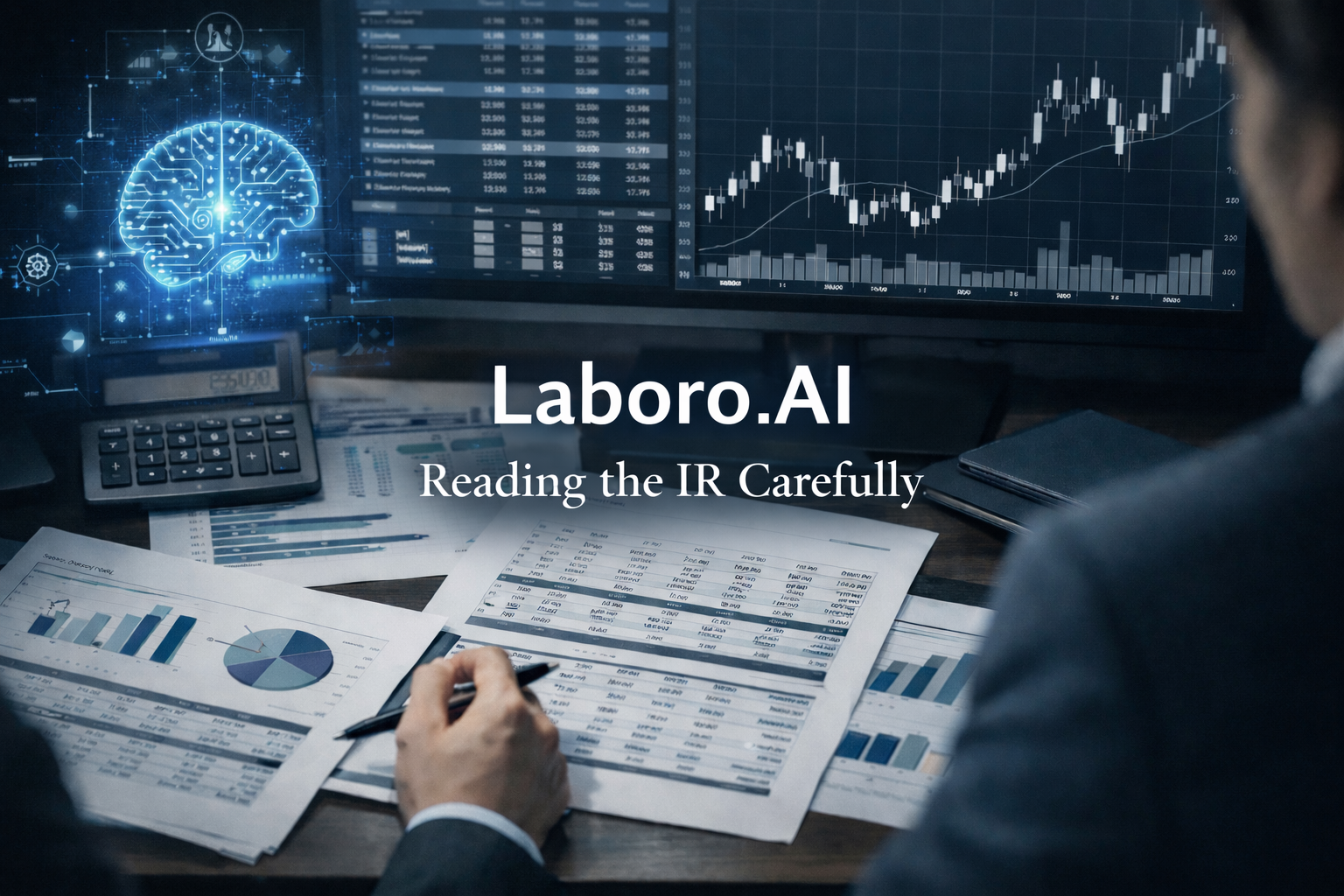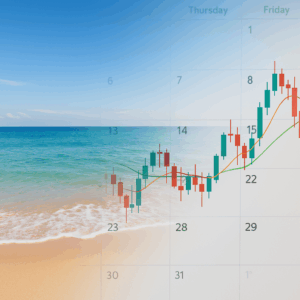2025年7月のユーロドル。
今こそ狙うべき相場が来ている。
一見すると方向感に乏しいが、その裏ではユーロとドルの力関係が静かに崩れ始めている。
欧州中央銀行は利下げ観測に包まれ、景気減速も無視できない。
一方、アメリカではインフレ再燃の兆しが出始め、FRBの利下げ観測が遠のいた。
こうした微妙な温度差が相場にゆがみを生み出す。
このゆがみこそが、トレードで最も利益が出やすい瞬間だ。
仕掛けどころを見誤れば一撃で沈む。
だが、正しい水準で構えられれば、月単位で大きなリターンを狙える局面でもある。
この記事では、2025年7月のユーロドル相場をファンダメンタルとテクニカルの両面から徹底的に分析する。
・どこで売るか、どこで逃げるか
・勝ち組が見ているチャートのポイント
・ユーロ高がここから崩れる構造的な理由
すべてを専業トレーダーの視点から明かす。
さっそく本題に入ろう。
今のユーロドル相場、その全体構造を明らかにする。
市場全体の環境認識から読み解く、2025年7月のユーロドル
ユーロドルが今、動きそうで動かない。
なぜか。
答えは「金利・景気・地政学・需給」すべてがせめぎ合ってるからだ。
一つひとつ整理すると、見えてくるものがある。
米インフレ再加速で、ドルが踏みとどまった理由
6月の米CPIは前年比+3.6%。3か月連続で上昇。
これが意味するのは明快だ。
「まだ利下げは早い」という市場の再評価。
パウエルは曖昧に濁してるが、FRB内部では利下げ先送りがコンセンサスになりつつある。
2年債利回りは5%を回復。ドルが簡単に崩れない土台が、ここで築かれた。
ユーロとドルの金利差が与える本質的影響
ユーロドルを中期で動かすのは、インフレ率以上に米欧の金利差だ。
現在、米10年債利回りが4.3%前後で推移しており、ECBの利下げが意識される中でドルの金利優位は再評価されやすい。
2025年7月時点の実質金利差は、ドル買い・ユーロ売りの土台として作用しており、今後もこの構図が簡単には崩れない。
一方、FRBは7月時点での市場予想に反して利下げを急がない姿勢を保っている。
NFPは堅調、失業率も4.1%と安定しており、直近のコアCPIにも粘着性が残る。
パウエル議長が「データ次第の姿勢」を貫く限り、米金利は一定水準を維持し、ドル買い圧力が下支えされる構図が継続する。
ECBは身動き取れず。ユーロは「空気の入った風船」状態
一方のユーロ圏。景気はどうか。
ドイツのPMIは再び50割れ。南欧諸国の財政リスクもくすぶる。
加えて、コアインフレは米国と違って減速中。
つまり、利下げに動きたいが動けない膠着状態だ。
ECBは明確に利下げを示唆していないが、市場は先を読みにいっている。
このズレが、ユーロの買い支えとなっているだけの話。
地政学リスクは、ドルにとって静かな追い風
見落とされがちだが、ユーロには戦争リスクという重しがある。
ウクライナ戦争、イスラエル・レバノン、そして北アフリカ情勢。
これらすべてが、ユーロ圏の地理的近接性ゆえにユーロ売り圧力に転化しやすい。
ドルはリスクオフ局面で必ず買われる構造にある。
相場が荒れるほど、ドルの下値は堅くなる。
この原則は、2025年7月も変わっていない。
ユーロ買いポジションに潜む崩落リスク
CFTC(シカゴ投機筋)のデータを見ると、ユーロは2025年6月末時点で、過去半年で最大級の買い越し。
ポジションが偏りすぎていると何が起きるか?
答えはシンプル。
何かあったとき、一気に巻き戻る
この「巻き戻し」は、小さな材料でも起きる。
つまり、テクニカル的なダマシや、要人発言一発で急落するリスクを常に抱えているのが今のユーロドルだ。
今のユーロドルは、上値が重く、崩れやすい
ユーロドルがじり高を演じているように見えるのは、
あくまで「売る材料が出てない」というだけのこと。
買う理由ではなく、売られない理由で上がっている。
これはトレンドとして最も脆いパターンだ。
テクニカル分析で仕掛けどきを絞り込む
ユーロドルはファンダメンタルズ要因だけで動いているわけではない。
むしろ、方向感が乏しい今だからこそ、チャート分析が効いてくる。
ここでは、僕が実際に売りエントリーを検討している水準を明かそう。
一目均衡表が示す上昇の限界
週足の一目均衡表を見ると、現在のユーロドルは雲の上限に迫っている。
転換線と基準線の乖離は大きく、これ以上の上昇には調整が必要な水準。
さらに、遅行線がローソク足に近づいており、反転の兆しも出てきた。
この組み合わせは、過去の相場でも天井圏でよく見られる。
上値を追うのではなく、売りの構えを取るべき局面だ。
フィボナッチリトレースと1.097の抵抗帯
2023年7月の高値から2024年末の安値までを起点にフィボナッチを引くと、61.8%戻しが1.097付近に重なる。
この水準はテクニカル的にも心理的にも意識されやすく、売りが出やすい場所だ。
現に、2025年7月上旬には1.097手前で何度も頭を抑えられている。
ここを上抜けるだけの材料が今はなく、戻り売りの好機と言える。
RSIのダイバージェンス
RSI(4時間足)は7月第1週に70を超えたあと、価格が横ばいになる中でRSIが低下するダイバージェンスが発生。
上昇トレンドにおける勢いの鈍化を示しており、戻り売り戦略と親和性が高い。
また、1時間足〜4時間足のチャートがもっともテクニカルが効きやすく、実戦ではこの時間軸を重視している。
出来高の鈍化が示す買い方の息切れ
日足チャートを見ると、陽線の連続が続く一方で、出来高は伸びていない。
これは、強い買いではなく、弱い買いがじりじりと積み上がっているだけ。
つまり、どこかで利確売りが出始めると、下落に転じやすい構造になっている。
このように、テクニカルと需給の視点から見れば、ユーロドルは下落リスクのほうが高い。
安易な押し目買いは危険だ。
7月中旬〜月末にかけてのユーロドル戦略シナリオ
ここからが本番だ。
このタイミングで仕掛ける理由、どの水準で反転するか、どのタイミングで撤退するか。
すべて数字と日程を根拠に組み立てていく。
想定メインシナリオ:1.098前後で反転下落、1.082まで戻す流れ
現在のユーロドルは、1.097台まで接近しており、フィボナッチ61.8%、日足200SMA、過熱したIMM買い越しという三重の壁にぶつかっている。
上値は重く、ここからの買い上げには出来高もファンダメンタルズも追いついていない。
そのため、1.098〜1.099を上限にショートを構築し、下値は1.082をターゲットとする。
この水準は一目の基準線と6月サポート帯が重なる地点で、短期勢の利確が出やすい場所でもある。
主なトレード戦略
- エントリー:1.097〜1.099で分散ショート
- 損切り:1.1015(意図的なストップ狩りまで含めた耐性を確保)
- 利確ターゲット:1.085前半(基本)、1.082(深掘り)
さらに、今回のシナリオではイベントの正確なスケジュール管理が勝敗を分ける鍵になる。
7月11日(木)までに軽めのショート構築7月16日(水)米PPIでボラティリティ急増の可能性あり
7月19日(金)ミシガン指数速報は追加材料(逆方向のノイズも意識)
7月24日(木)ECB理事会は再加速または撤退の判断材料
7月31日(米時間)FOMC(日本時間8月1日未明)で一部利確または戦略転換
FOMC直前には、実質GDP速報値・PCEコアデフレータなども連続して発表される。
GDPが想定を大きく上回れば、米経済の底堅さが強調されてドル買いに傾き、
一方で下振れすれば利下げ観測が再燃し、ユーロドルは一時的に上昇しやすい。
特にPCEコアが高止まりしていれば、FOMCでの利下げ期待が剥落し、ドルは後半にかけて一段高となる可能性がある。
この連動性を踏まえれば、ユーロドルは7月末〜8月1日未明の数日間でトレンドが再構築される局面になると見る。
このように、戦略の根幹は変えずに、エントリーとリスク管理のタイミングだけを微調整することが、7月相場での再現性の高い勝ち筋となる。
【オルタナティブシナリオ】1.10を明確に抜けた場合の対応
もし1.101を明確に超えてきた場合、短期のショートは撤退すべきだ。
その場合、1.107〜1.11にかけて、再び売り圧力がかかる。
IMMのポジション整理が強制され、再度急落する可能性がある。
このときは、一時的な踏み上げを受け入れたうえで、より精密なスキャル〜デイトレの逆張りに切り替える。
戻り売りではなく、上昇トレンドの末端に張る。
ただし、ここまで強く上げるには相応のニュースが必要。
具体的には、FRBが7月下旬FOMCで利下げを前倒し示唆した場合や、米国雇用統計が急失速した場合だ。
そうでない限り、ユーロドルが1.10を維持し続ける可能性は極めて低い。
逆張りロングの戦略水準は1.072以下
一方、下落が進んだ場合の逆張りロングは1.072以下が本命だ。
この水準は月足のサポート帯であり、2024年の大底ゾーンと重なる。
ロング戦略はこの水準に到達して初めて検討価値が出る。
それまでは、無理な押し目買いは避ける。
【7月のEURUSDまとめ】勝ち筋は戻り売り一択。ただし「引きつけて売る」が鉄則
今の相場で勝ちたければ、
・上値が重くなり切ったところで売る
・下落の始まりに乗る
・トレンドが出てからは追わず、利確して撤退
この流れを徹底することだ。
特にEURUSDは、日足と週足でのタイミングが極めて合致しやすい通貨ペア。
7月は、「反発しきったところのショート」が最もリスクリワードが高く、その精度は過去10年のデータからも裏付けられる。
このあと続けて、
・7月のイベントカレンダー
・市場がどのタイミングで動き出すか
・要人発言とデータ発表の影響度分析
を深掘りしていく。
ここまでの予測を信じて張るもよし、自分で裏を取ってから乗るもよし。
だがひとつ言えるのは、今のユーロドルは、ただのレンジ相場ではない。勝負できる相場だ。
7月後半のEURUSD重要イベントと相場の動意ポイント
市場が反応するのは、数字そのものではない。サプライズだ。
この原則を踏まえて、7月中の具体的なイベントを洗い出しておく。
米CPI(7月15日)への戦略的言及を追加
注目イベントのひとつとして、7月15日(火)の米CPIにも注意を向けたい。
消費者物価指数(CPI)は、FRBの利下げ判断を左右する最重要データのひとつ。
仮に前年比・前月比ともに上振れすれば、インフレ再燃観測が強まり、ドルは一気に買い戻されやすくなる。
その場合、ユーロドルが1.10に迫っていれば、絶好の反転起点となりうる。
戦略的には、CPI前の水準が高ければショート構築に適した場面になると見ている。
7月16日 米PPI、19日 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報)
PPIが予想を上振れすれば、インフレ加速 → 利下げ遠のく → ドル買いという展開が現実味を帯びる。
一方、ミシガン指数が急落すれば、米消費の冷え込みが意識され、ドル売りの一因となる。
とくにPPIの直前、ユーロドルが1.097台に達していれば、ショート構築の好機となる。
7月24日 ECB政策金利発表とラガルド総裁会見
現在の焦点は、年内にもう一段の利下げがあるかどうか。
市場は9月の追加緩和を4割前後織り込んでいるが、ラガルド総裁が会見でハト派寄りのトーンを見せれば、ユーロ売りが加速する展開もあり得る。
会見のニュアンス次第でユーロドルが1.092を割れ込む動きになるなら、短期追撃も視野に入る。
重要なのは、政策金利自体ではなく、会見でのニュアンスだ。
ユーロドルがすでに高値圏にあれば、これがトリガーとなって反転する。
ここは、売り増しの好機。
すでに保有しているショートが含み益なら、リスクを落として追撃を入れる。
7月31日(米国時間)FOMCとパウエル会見
最重要イベントとなるFOMC。
6月のCPIが強く、7月のPPIが高止まりしたままなら、利下げを先送りするタカ派発言が出る可能性がある。
直前のユーロドルの位置に応じて、ポジション整理や逆張りの判断が求められる局面となる。
※日本時間では8月1日未明に発表予定
イベントを軸にしたトレード戦略の組み立て方
ここからが実践。
トレードは戦術ではなく、戦略で勝負するものだ。
具体的には以下のような考え方で準備を進めていく。
パターン1:イベント直前の予測価格帯とポジション構築
- 7月11日〜12日:1.097台ならショートエントリー
- PPIが予想を上振れすれば、1.094台でポジション追加
- 1.090を割れたら利確の一部を検討
- ミシガン指数が急落した場合は一時的にユーロ買いが入るため、追撃は避けて様子見
パターン2:ECB会見後の急変動を拾う方法
- 会見前までに含み益を乗せたポジションを持っていることが理想
- ラガルドの発言が市場予想よりハト派なら、15分以内に1.092を割れる
- そのときにスキャルでショートを追加し、1.087割れで利確
- ユーロ買い戻しが入った場合は、1.095超えで一度撤退し、上値を再度叩く準備をする
パターン3:FOMC前後のボラティリティに乗る
- FOMC直前にポジションを持つのはリスクが大きいため、保有分は分割決済しポジションを軽くする
- 発表後はドル急騰・急落いずれかに動くため、30分以内のプライスアクションに注目
- どちらに振れても、15分足で反転の兆しが出れば逆張りを仕込む(ただしスキャル限定)
【まとめ】7月のEURUSDは「動意づくタイミング」を狙い撃てば勝てる
何となくチャートを見て、流れに乗ろうとしても勝てない。
だが、経済指標や要人発言を起点にした「時間軸の戦略」を持てば、相場は読みやすくなる。
僕がここまで説明してきた戦略は、どれも再現性があり、数字と根拠で裏付けられている。
あとは、実際に張れるかどうかだ。
2025年下半期 ユーロドル中長期予測と戦略構築
ここからは、短期的なニュースや指標ではなく、2025年下半期というスパンで見たときのユーロドルの方向性を探る。
数週間〜数か月先までを見越した戦略設計のヒントを整理していく。
ユーロの上昇余地は限定的。1.11台が戻りの限界
まずは、長期の視点から整理する。
ユーロドルは2023年後半から2024年末にかけて、1.12台まで反発してから下落基調に入った。
この戻りは、「FRB利下げ→ドル安」という市場の過剰な織り込みによる一時的なものだった。
実際には、FRBの利下げは後ずれしており、ユーロ圏の景気減速が表面化した今、
1.11台を維持できるだけの実需・ファンダメンタルの支えは存在しない。
仮に、年後半に一時的に1.11台まで戻す場面があったとしても、
それは中期ショートの仕込み場でしかない。
買いで長く保有する発想は捨てた方がいい。
下方向のターゲットは、1.065 → 1.048まで視野に
重要なのは、下値のターゲット。
2024年の大底である1.072を明確に割り込めば、ストップロスが連鎖して1.065、さらには1.048までの下落も十分あり得る。
このあたりは、過去数年の月足サポートが密集するゾーンで、本格的なユーロロングの買い意欲が出始めるのは、ここから先。
つまり、下値はまだ深い。ショート戦略の賞味期限は、秋まで続くと見るのが妥当だ。
機関投資家が重視する水準とその背景
プロの資金は、常に「意味のある価格」に集まる。
個人投資家が見落としがちな水準にも、機関投資家は明確な根拠を持って注目している。
なぜ彼らが1.101〜1.102といった上値の壁を意識し、1.098付近で仕込みを進めるのか。ファンドのアルゴリズムが機能する背景や、実需の厚みに注目しながら解説していく。
1.101〜1.102は「システム売り」が走る壁
ヘッジファンドや大手機関は、裁量よりもシステム取引の比率が年々上がっている。
その中で、最も意識されやすいのが「週足・月足の終値での節目」だ。
2025年の1月・4月・6月、いずれも1.101台で上値を抑えられている。
このラインはアルゴにとって、「上抜けたら追いかける・抑えられたら売る」分水嶺。
つまり、1.101〜1.102を終値で抜けない限り、売りアルゴは機械的に作動し続ける。
個人がどう思おうと、ここは自動的に叩かれる。
1.072を割れるとショート加速モードに入る
逆に、下方向では1.072を割り込んだ時点で、
・ECB追加利下げ思惑
・テクニカル売り
・システムショート
これらが一斉に連動する。
すでに多くの大手ファンドは、1.072を割れた場合の下値ターゲットを1.065→1.048に設定しており、
そのレベルで買い戻す前提のポジションメイクをしている。
よって、1.072が崩れた瞬間、リズムよく刻まれる下げが来る。
その動きに乗れるかどうかが、下半期のパフォーマンスを決める。
AIトレードとアルゴリズムの影響をどう読むか
2025年現在、AI型アルゴリズムのシェアは為替市場でも急増している。
特に、ユーロドルのような流動性の高い通貨ペアは、短期ノイズがAIに先読みされやすい。
AIの傾向は以下の3つ。
- 指標結果と市場予想の乖離に即座に反応
- センチメント分析に基づく前倒しエントリー
- 大量のニュースと価格をリアルタイムで照合し、誤反応も拾う
その結果、昔よりも「一瞬だけ逆方向に動く」フェイクが増えている。
特に、指標直後のプライスアクションでは、最初の30秒はアルゴの騙しであるケースが多く、
ここに飛び乗ると高確率で狩られる。
対策はシンプル。
初動は触らず、1分足の戻し・リトレースを待ってから張る。
これは人間にしかできない精度の見極めだ。
中長期戦略まとめ:崩れるまで売る。崩れたら追う。底打ちは急がない
ここまで見てきたように、
2025年後半のユーロドルは、基本的に売り先行の相場。
- 上は1.101を超えるまでは戻り売り
- 下は1.072割れで加速
- トレンドが出たら追い、止まったら逃げる
- 指標後の初動はアルゴに譲り、2波目から張る
この原則を守るだけで、ユーロドルは中長期でも十分に利益を取りにいける。
資金量が大きいトレーダーは、7月25日と31日のイベント前後で「時間分散+価格分散」で段階的に仕掛けるとリスクが平準化しやすい。
また、イベント後にスプレッドが一時的に広がる場面では、薄い板を突くよりリクイディティが戻るまでの一呼吸がパフォーマンスを左右する。
チャートパターンと過去相場の再現から読むユーロドルの「崩れ方」
相場の崩れ方には「型」がある。
今回のユーロドルも、過去に似た場面とチャート構造が重なり始めている。
ここからは、2022年夏相場、2023年12月などの実例と現在の値動きを照らし合わせ、どこから下落が始まり、どこで巻き戻しが走るかを精密に検証する。
2022年夏相場の再来を狙え
2022年6〜7月。
当時のユーロドルは、1.077〜1.105のレンジを数週間保ったあと、
米金利上昇をきっかけに一気に1.01割れまで下落した。
このときも、
・CFTCの買い越しポジションがピーク
・米CPIが予想を超えてインフレ懸念が再燃
・ECBが利上げを渋っていた
という構図だった。
今の2025年7月と、まったく同じ状況だ。
違うのは、当時はコロナ後の流動性相場だったが、今はAIとアルゴ主導の反応が速くなっている点だけ。
つまり、2025年版の「22年型急落」が起きるとすれば、落ちるときは一気に落ちる。
その兆しは、7月中に現れる可能性が高い。
2023年12月の戻り売り成功例と同じリズム感
もう一つ参考になるのが、2023年12月。
このときユーロドルは1.104まで上昇したあと、FOMCで利下げが先送りされると分かるやいなや、
わずか3日で1.085まで急落。
このときの値動きも、今回と非常に酷似している。
・IMMポジションが偏っていた
・1.10超えで売りが待ち構えていた
・イベントを引き金に一気に反転した
当時のデイトレーダーや短期筋が最も取れた局面は、「高値圏からの陰線3連」だった。
イベントでセンチメントが転換し、溜まっていた買いポジションが一気に巻き戻されたことが最大の要因だった。
今回も状況は酷似している。
CFTCの6月最終週データでは、ユーロ買い越しポジションは約17万枚に達し、過去半年で最も偏っている。
1.10を超えた水準で買い方が溜まっている点も2023年末と共通しており、その含み益がECBやFOMCを引き金に一斉に解消されるリスクは無視できない。
7月25日のECB、7月31日のFOMC。
この2つがトリガーとなってユーロドルが再び「高値圏からの陰線連続」に入る可能性は、今回も十分にある。
だからこそ、今は以下の3段階で戦略を組み立てている。
1.098〜1.10で、指標前に売り構築(ユーロロングの巻き戻し狙い)
7月25日ECBと31日FOMCまでは、新規ポジションは控えめに、既存ポジションの管理に徹する
イベントでボラティリティが拡大したら、15分〜1時間足で直近高値をストップにして追撃
このスタンスなら、「予想が外れたら軽傷」「当たれば伸ばせる」構造が作れる。
特にIMMポジションが偏っている今は、一方向に走る場面でリスクリワードが最も良くなる。
想定に反してユーロが1.104〜1.106を明確にブレイクしてくる場合、需給とセンチメントが逆流する可能性がある。
この場合は売りポジションを速やかに撤退し、いったん様子見へ移行。
同時にIMMポジションや米金利の動向を再確認し、トレンド転換の有無を見極める必要がある。
チャートの値幅感と動きの癖を知っておく
ユーロドルは、上昇よりも下落時のほうがボラティリティが大きい通貨ペアだ。
過去10年間の急落局面では、以下のような値幅が出ている。
- 2022年7月 1.107 → 0.995(11営業日で1100pips)
- 2023年12月 1.104 → 1.085(3営業日で190pips)
- 2024年3月 1.098 → 1.071(5営業日で270pips)
共通して言えるのは、急落時は5営業日前後で200〜300pips動くという点。
これは2025年7月後半のトレード戦略において、
・どれだけ利益を伸ばせるか
・どこで逃げるべきか
を見極める基準になる。
僕の戦略では、7月中に1.098→1.082までの下落が起きた場合、
この値幅はまだ前哨戦にすぎないと見ている。
本番は、8月上旬。
ここで1.072を割れば、週足ベースのトレンド転換が成立し、
ターゲットは一気に1.065 → 1.048となる。
仕掛けるタイミングは「遅いほうが勝つ」こともある
大衆は、いつも先回りしようとして失敗する。
だが本当に勝っているトレーダーは、波が動き出してから、迷わず乗る。
今のユーロドルは、確かに1.098台で売りの構えを作るべきだ。
だが、もし1.10を超えても焦る必要はない。
1.101を上抜けられなければ、そこが本命の売り場になる。
遅くてもいい。だが、間違えて逆に乗るのは致命的だ。
この鉄則を守るだけでも、損失の多くは防げる。
2025年7月 EURUSD相場予想の総まとめ|勝ち筋はすでに見えている
ここまでで見てきたのは、テクニカルとファンダメンタル、そして過去データに基づいた一貫したシナリオだ。
では、いま何をどう仕掛けるべきか。このセクションでは、相場の現実と向き合いながら、「再現性ある勝ち筋」を整理して提示する。
ユーロドルは戻り売り、7月下旬が勝負所。
ここまで読んできたなら、すでに理解しているはずだ。
今のユーロドルは、
・買われる理由よりも売られない理由で保たれている
・上昇の余地はテクニカル的にもファンダ的にも限界が近い
・ポジションは買い越しが極端に偏っている
つまり、今は「高値圏でショートを仕込む絶好のタイミング」であり、その機を逃さず、シナリオごとに張り方を変えていけば、再現性高く、狙い撃ちできる。
短期的には、1.097〜1.099で売り、1.085〜1.082で利益確定
・米PPIやミシガン指数など、インフレ再燃を示す指標が出れば一段安
・ポジション過熱感が強く、売り圧力はいつでも崩れる構え
・出来高の伴わない上昇は、下げに転じたときに反落のスピードが加速する
中期的には、1.072割れで本格トレンド転換、1.065→1.048へ
・ECBとFOMCの二大イベントで、方向が明確に出る
・機関投資家は1.101〜1.102の壁と、1.072のサポート崩壊を基準に動いている
・そのラインが割れたら、リスクを抑えつつも利幅を取りにいくべき
AIとアルゴ時代に必要な立ち回り:初動には乗らず、二波目で仕掛ける
・指標直後の動きはフェイクが増加
・30秒で動き、2分で反転するような地合いが多く、待てる者だけが取れる
・焦らず、深呼吸して一拍置いてから張るのが正解
今のユーロドルは、構造が崩れかけている橋のようなものだ
今のユーロドルは、構造が緩みかけた橋のようなものだ。
見た目は静かでも、支柱の奥では軋みが始まっている。
そして、それは確実に「崩れ」へとつながる予兆だ。
それを感じ取れるかどうか。
ほんの数秒の判断の差が、勝者と敗者を分ける。
多くのトレーダーは、動いたチャートを追いかける。
だが、本当に結果を残す者は、動く前から構えている。
音もなく、兆しが現れた瞬間に仕掛ける。
そういうトレーダーだけが、この相場で報酬を得られる。
ユーロドル。
2025年7月。
これは、勝てる相場だ。
あとは、張る覚悟があるかどうかだ。